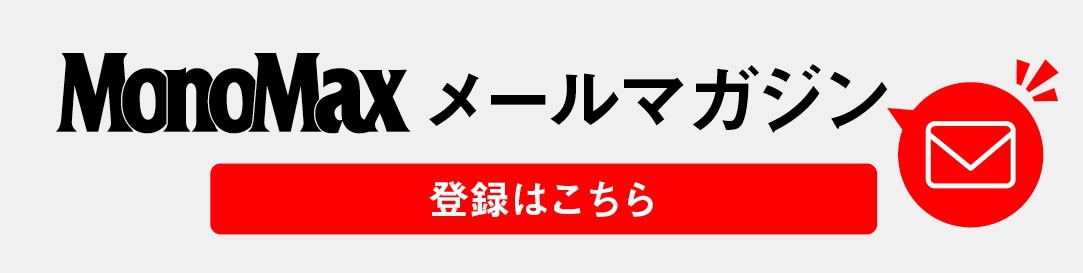今年は2月2日が節分です。地球が太陽のまわりを1周するのが365日からずれることで節分の日も3日だったり4日だったりするようですが、今年は124年ぶりに節分が2月2日になったことでも話題となりました。近年は節分といえば恵方巻を食べる文化がすっかり広まりましたが、そもそもなぜ恵方巻を食べるのでしょうか?食の専門家であるスギ アカツキさんに聞きました。
【恵方巻の廃棄、減らせる?】ファミマの「涙目シール」商品を救え!日本初上陸の“フードロス削減アプリ”体験レポ
約50年前に突如はじまった「恵方巻」文化は海苔を売るため!?

「恵方巻というのは日本における食文化の歴史を掘り下げても出てこない、直近50年くらいのもの。食品会社が販促のために始めたイベントなんです。1977年に関西の海苔屋さんが、“もっと海苔を食べてほしい”という想いから、江戸時代から明治時代にかけて商売繁盛や無病息災を願って食べられていた太巻き寿司に注目したそう。海苔をたくさん消費する食べ物=太巻きだったのがはじまりだと言われています。当初は『節分の日に巻き寿司を丸かぶりすると幸運が巡ってくる』というチラシが配布されていました。
その後1998年に、関西ローカルだった『丸かぶり寿司』をセブン-イレブンが『恵方巻』と名付けて全国展開しました。それまで節分=豆まきという文化はあったものの、小売業界にとって豆を売る以外あまり販促にならなかったこともあり、コンビニ以外にも広がっていきました。色々な具材も入っていて楽しいですし、日本人はお寿司好きですし、食習慣としても好まれやすかったんですよね」(スギアカツキさん)
―――もともとは約50年前に海苔屋さんの販促として始まったのですね!そして全国に広めたのはセブン-イレブンとは……納得です。しかしクリスマスやひな祭りなどの他のイベントに比べ、恵方巻は「この方角を向いて食べろ」「食べ終わるまでしゃべるな」などルールが多い気がしますが何故なのでしょうか?
「恵方巻の具材はおめでたいものばかりで、一般的に七福神にちなんで7種類入れると縁起が良いとされています。たとえば、かんぴょうは長寿や健康を願う・しいたけは厄除けや身を守るという意味があります。そんな願掛けもあって、『喋ると口から福が逃げちゃう』ので黙って食べるのです。しかも『恵方巻を切ると縁が切れる』ことから、一人で1本を食べ切ります」(スギアカツキさん)
―――海苔を売るために始まったわりには願掛け要素も強いからなのですね。しかし、そのルールによる「縛り」がよりエンタメ性を高めている気もします。だから定着したのかもしれませんね。
この記事のタグ
この記事を書いた人
ライター松本果歩
インタビュー・食レポ・レビュー記事・イベントレポートなどジャンルを問わず活動するフリーランスライター。コンビニを愛しすぎるあまり、某コンビニ本部員となり店長を務めた経験あり。日本酒・焼酎・発酵食品が好き。
Website:https://monomax.jp/
お問い合わせ:monomaxofficial@takarajimasha.co.jp
モノマックスの記事をシェアする
関連記事